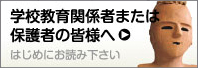HOME > 展示紹介 > 芝山象嵌と横浜芝山漆器

|

企画展「芝山象嵌と横浜芝山漆器」
◎展示期間:2009年11月5日(木)〜12月6日(日)
主催:芝山町立芝山古墳・はにわ博物館
後援:横浜芝山漆器研究会
開催の趣旨
象嵌とは、素地を彫りくぼめ、そこに金具や貝などで形を象ったものを嵌め込んで装飾効果を高める工芸手法である。そのうち、貝や象牙、珊瑚、鼈甲、翡翠などを用いて花鳥や人物などを表現する技法が芝山象嵌で、精巧で立体的な装飾性に特色がある。
芝山象嵌は、安永年間(1772〜1781)に上総国芝山村(現千葉県山武郡芝山町)の小野木専蔵(小野木仙蔵とも)によって考案され、江戸に出て芝山専蔵と改名し、この技法を広めたので芝山象嵌と呼ばれている。
作品には、印籠、根付け、置物、屏風、飾り棚など大小様々あり、明治時代には欧米への輸出用工芸品として人気を博した。こうして、芝山象嵌の職人が貿易港の横浜へ集まるようになり、漆の中に嵌め込む技法として横浜独自の発展を遂げ、横浜芝山漆器と呼ばれるようになった。関東大震災や戦争の影響により職人が離散したため、現在では横浜芝山漆器の後継者も少なくなっている。
現在、芝山象嵌発祥の地とも言える芝山町には、文化2年(1805)作の芝山象嵌扁額(町指定文化財)が残されている。そこで、企画展では、芝山象嵌扁額とともに、輸出された作品、芝山象嵌を修得し独自の木象嵌の技法によって人間国宝となった秋山逸生の作品、芝山象嵌の技法を継承している横浜芝山漆器の作品を集めて紹介していくことにしたい。
構成と展示作品
(1)芝山象嵌のはじまり
(1)内国勧業博覧会出品作品
(3)輸出工芸品としての芝山象嵌
- 象牙台付花瓶一対(個人蔵)
- 四曲屏風(金子晧彦氏)
- 桜文様屏風(金子晧彦氏)
- 飾棚(金子晧彦氏)
- 飾り棚(金子晧彦氏)
- 桜花鳥重貼り四曲屏風(金子晧彦氏)
- 楕円壁掛(金子晧彦氏)
- 吊り花籠文様壁飾り(金子晧彦氏)
- 額縁(金子晧彦氏)
- 花籠文様四曲屏風(金子晧彦氏)
- 花鳥文様二曲屏風(金子晧彦氏)
- 花鳥文様飾額(金子晧彦氏)
- 花鳥文様飾額(金子晧彦氏)
(4)秋山逸生作品
- 菱華文象嵌長手箱(千葉県立美術館)
- 蕾芝山象嵌額(千葉県立美術館)
- 蝶貝象嵌小箱(千葉県立美術館)
- 木画箱(千葉県立美術館)
- 蝶貝象嵌箱(千葉県立美術館)
- カンナ芝山象嵌襟飾(千葉県立美術館)
- 對縞黒壇筆筒(千葉県立美術館)
(5)横浜芝山漆器
- 呂色漆芝山青貝蒔絵料紙箱(横浜市技能文化会館)2点
- 芝山師宮崎輝生作額絵(横浜芝山漆器研究会)4点
- 中華街額絵(横浜芝山漆器研究会)
- 神奈川県立博物館額絵(横浜芝山漆器研究会)
- 横浜全景額絵(横浜芝山漆器研究会)
- 横浜家具<小箪笥と化粧台>(横浜芝山漆器研究会)
- 制作工程見本(横浜芝山漆器研究会)
関連行事
■講演会■
平成21年11月15日(日)14時〜
「芝山漆器の変遷について」赤堀郁彦氏(横浜芝山漆器研究会会長)
■横浜芝山漆器展示即売会■
横浜芝山漆器研究会会員の作品を展示即売(企画展開催中)

※催し物の展示品の一部が異なることがあります。
ご了承くださいませ。
|

 |
展示紹介のページはこれで終わりです
はにわ祭のページへ
|
 |



![]()